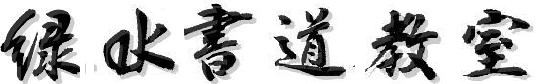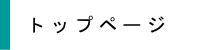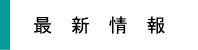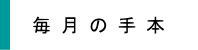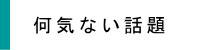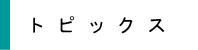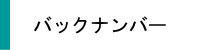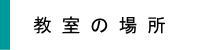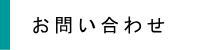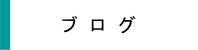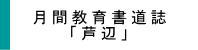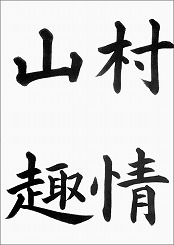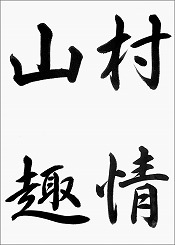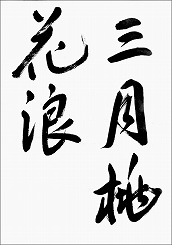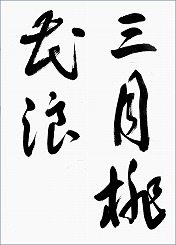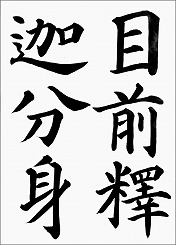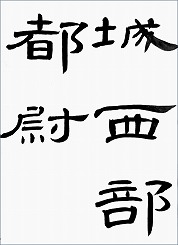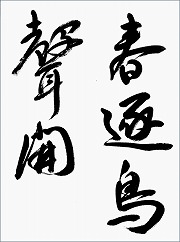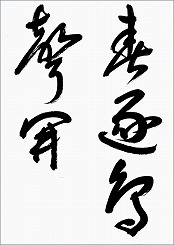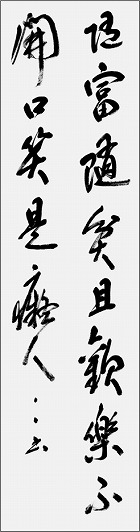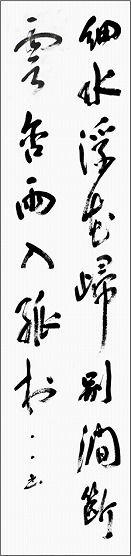|
|
芦辺月例課題(令和6年3月号課題) |
|
|
|
|
|
| 初級【漢字二体】 |
|
|
|
|
| 楷書 |
|
行書 |
|
|
|
|
|
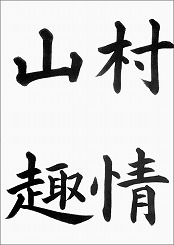 |
|
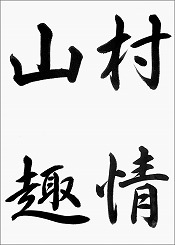 |
|
|
|
|
|
|
| 村情山趣(そんじょうさんしゅ) |
| 村の風情に山の趣。山の景色を見て「山の趣(おもむき)」に故郷を思い出す |
|
| 【出典:段成式・唐)】 |
|
|
|
|
|
|
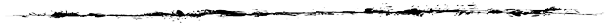 |
|
|
|
|
| |
| 上級【漢字二体】 |
|
|
|
|
| 行書 |
|
草書 |
|
|
|
|
|
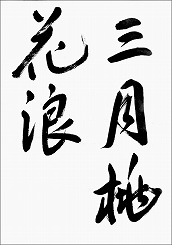 |
|
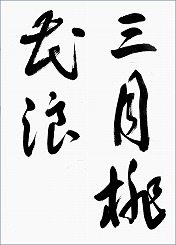 |
|
|
|
|
|
|
| 三月桃花浪(さんがつとうかのなみ) |
| 三月になり桃の花が咲くころ、川は波立ってきた |
| |
| 【出典:春水・(杜甫・唐)】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
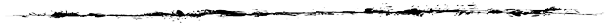 |
|
|
|
|
|
| 【細字】 |
 |
|
|
|
|
|
|
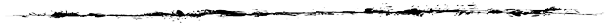 |
|
|
|
| |
| 【臨書】 |
|
|
|
|
| 楷書 |
|
隷書 |
|
|
|
|
|
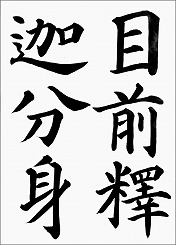 |
|
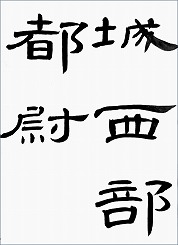 |
|
|
|
|
|
| 多宝塔碑(顔真卿) |
|
曹全碑(後漢) |
|
| |
|
|
|
| 宛在目前釋迦分身 |
| 読み:もくぜんにあるがごとく |
| しゃかのぶんしん・・・ |
| 眼前にあるかのように現れ |
| 釈迦の分身が・・・ |
|
|
|
|
|
| 金城西部都尉 |
| 読み:きんじょうせいぶとい |
|
| *金城…中国にかつて存在した郡 |
| *都尉…郡の軍事を司る地方長官 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
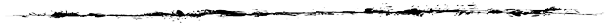 |
|
| |
|
|
| |
|
| 師範【漢字二体】 |
|
|
|
|
| 行書 |
|
草書 |
|
|
|
|
|
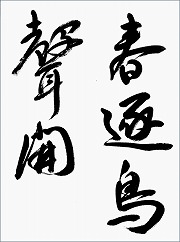 |
|
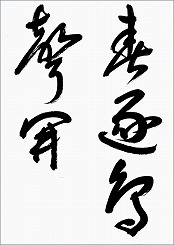 |
|
|
|
|
|
|
| 春逐鳥聲開(春は鳥声を逐(お)ってひらく) |
| |
| 春が鳥のさえずりを追うようにして訪れる |
| |
| 【出典:首春・(李世民・隋末~初唐)】 |
|
|
|
|
| |
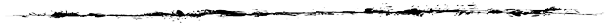 |
|
| |
|
|
| 【条幅】 |
|
一般課題 |
|
|
|
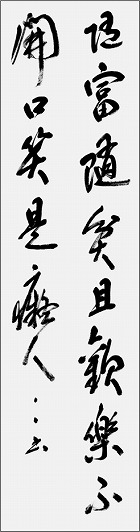 |
|
| 蝸牛角上争何事 石火光中寄此身 |
| 随富随貧且歓楽 不開口笑是癡人 |
|
| 【読み】 |
| 蝸牛(かぎゅう)角上(かくじょう)何事をか争う |
| 石火(せっか)光中此の身を寄す 富に随い |
| 貧に随いて且(しばら)く歓楽せん 口を |
| 開いて笑わざるは是れ痴人 |
|
| 【意味】 |
| 世間の人は、かたつむりの角の上のような小さな世界に |
| 生きていったい何を争うのか。火打ち石を打って発する |
| 火花のようにはかなく、人はこの世に生まれて死ぬ。 |
| 富んでいる者、貧しい者、それなりにとりあえずまあ、 |
| 楽しもう。大きく口をひらいて笑わないやつは、たわけ |
| ものだ。 |
| |
| *蝸牛…かたつむり *石火光中…石火は火打ち石を打って発する火。 |
| 極めてわずかな時間のたと *且…とりあえず |
| *開口笑…大きく口を開けて愉快にわらう。 *痴人…愚か者 |
|
| 【出典:対酒(白楽天・中唐)】 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
師範課題 |
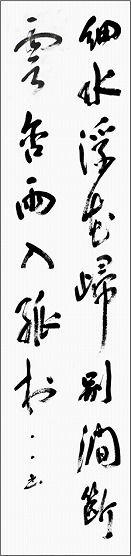 |
|
| 惜春連日酔昏昏 酔后依裳見酒痕 細水浮花帰別澗 |
断雲含雨入孤村 人閑易有芳時恨 地迥難招自古魂
|
| 慙愧流鶯相厚意 清晨猶為到西園 |
| 【読み】 |
| 春を惜しみ連日酔うこと昏昏(こんこん)たり 酔后 |
| 依裳に酒痕を見る 細水 花を浮かべて別澗に帰り |
| 断雲 雨を含み孤村に入る 人 閑かにして芳時の |
| 恨みあることやすく 地迥(はる)かにして自(おの) |
| ずから古魂招き難し 慙愧(ざんき)す流鶯の相厚意 |
| するに 清晨猶 為に西園に到る |
| 【意味】 |
| 行く春を惜しみ、連日酔っぱらって酔昏し、目が |
| 覚めると服はしみだらけ。細い川には散り行く |
| 花が漂い別の渓谷へと流れていく。ちぎれ雲が雨 |
| を伴って寂しい村に漂い入っていく。退屈な春の |
| 白昼の日々が白々と過ぎ去り、遠く離れた異郷 |
| では古代の魂を呼び戻すのが難しい。一番うれ |
| しいのは、流鶯が深い愛情を掻き立て、早朝に |
| わざわざ西園に飛んで来てくれること。 |
| *惜春…行く春を惜しむこと。 *孤村…寂しい村 |
| *昏昏…意識のはっきりしないさま *迥…はるか。遠い。 |
| *芳時…春の季節 *慙愧…感謝すること |
| |
| 【出典:春尽(韓愈・唐)】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毎月の手本のページへ |
|
|