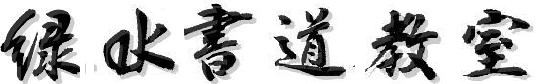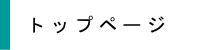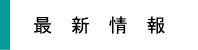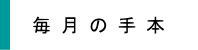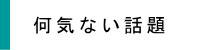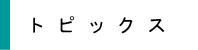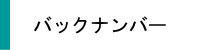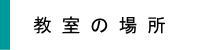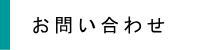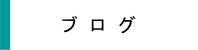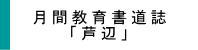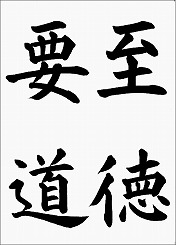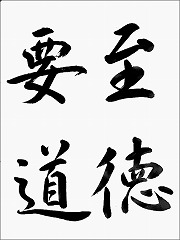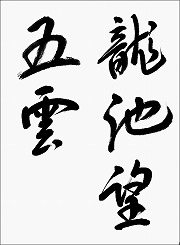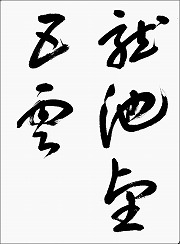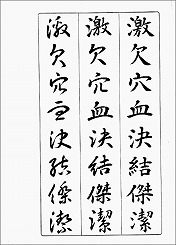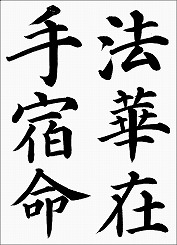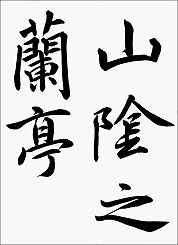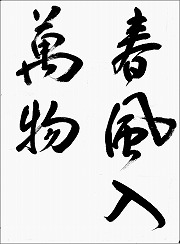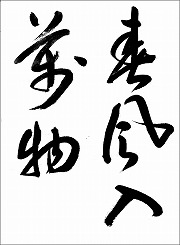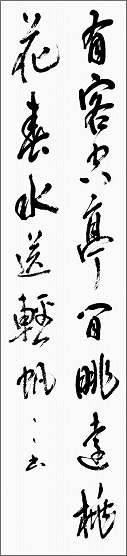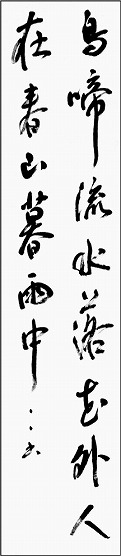|
|
芦辺月例課題(令和5年4月号課題) |
|
|
|
|
|
| 初級【漢字二体】 |
|
|
|
|
| 楷書 |
|
行書 |
|
|
|
|
|
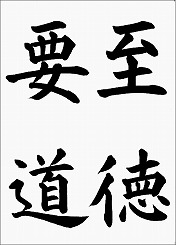 |
|
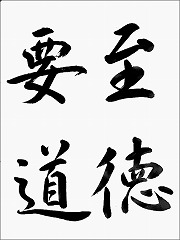 |
|
|
|
|
|
|
| 至徳要道(しとくようどう) |
| この上ない立派な徳と大切な教え |
|
| 【出典:孝経(開宗明義)】 |
|
|
|
|
|
|
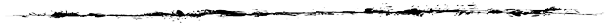 |
|
|
|
|
| |
| 上級【漢字二体】 |
|
|
|
|
| 行書 |
|
草書 |
|
|
|
|
|
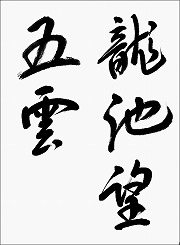 |
|
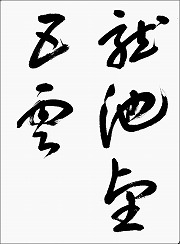 |
|
|
|
|
|
|
| 龍池望五雲(りゅうちごうんをのぞむ) |
| 春に龍池の水が暖かに満ち、たなびく五雲を望むことができる |
| *五雲…仙人や天女が遊ぶところにかかる五色の雲(青、赤,黄、白、黒) |
| 【出典:書杜少陵詩后・繆日芑(ぼくえつき)】 |
|
|
|
|
|
|
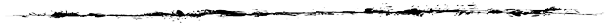 |
|
|
|
|
|
| 【細字】 |
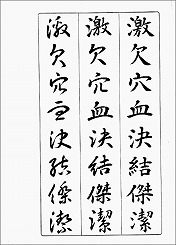 |
|
|
|
|
|
|
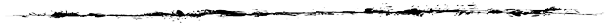 |
|
|
|
| |
| 【臨書】 |
|
|
|
|
| 楷書 |
|
行書 |
|
|
|
|
|
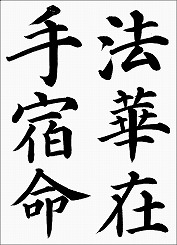 |
|
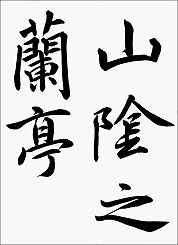 |
|
|
|
|
|
| 多宝塔碑(顔真卿) |
|
蘭亭序(王羲之) |
|
| |
|
|
|
| 法華在手宿命 |
|
会稽山陰之蘭亭 |
|
| 読み:ほうけ てにありしゅくめいを… |
|
読み:(かいけい)さんいんのらんてい |
|
| 法華経を手中にした。前世から備わ |
|
会稽山の北側の蘭亭 |
|
| っていた悟りは… |
|
*会稽山陰…会稽山の北 |
|
|
|
*蘭亭…別荘の名 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
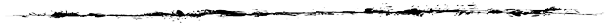 |
|
| |
|
|
| |
|
| 師範【漢字二体】 |
|
|
|
|
| 行書 |
|
草書 |
|
|
|
|
|
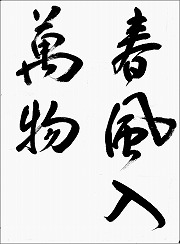 |
|
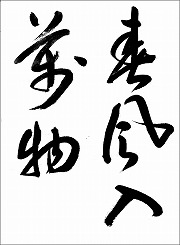 |
|
|
|
|
|
|
| 春風入萬物(しゅんぷうばんぶつにいる) |
|
| 春風が天地の間のあらゆるものに吹き渡っている |
| |
| 【出典:贈答劉御史雲卿(元好問・金末元初)】 |
|
|
|
|
| |
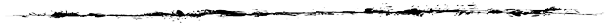 |
|
| |
|
|
| 【条幅】 |
|
一般課題 |
|
|
|
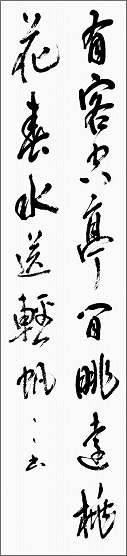 |
|
| 青山一角夕陽銜 隔断喧囂境不凡 |
| 客有空亭閒眺遠 桃花春水送軽帆 |
| |
| 【読み】 |
| 青山の一角 夕陽を銜(ふく)み 喧囂(けんごう)を |
| 隔断(かくだん)して境(つい)に凡(ぼん)ならず |
| 客有り 空亭 閒眺(かんちょう)遠く 桃花 春水 |
| 軽帆(けいはん)を送る |
|
| 【意味】 |
| 青山の一角に夕陽が輝いている。ここは世間の喧騒 |
| から離れた佳境の地。人が一人遠く人けのないあずま屋 |
| を眺め 桃の花が咲く春の江には帆船が進んでいく。 |
|
| |
| *題画…山水などの絵画に詩文を題し書くこと |
| *喧囂…騒がしいこと *境…竟に通ず |
| *空亭…ひっそりとしたあずま屋 |
| *閒眺…静かに眺めること *軽帆…早く走る帆船 |
| |
| 【出典:題画(邵璸(しょうひん)・清) 】 |
|
| |
|
|
| |
|
師範課題 |
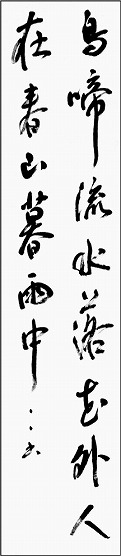 |
|
| 漫道桃源路不通 渓行十里道心空 |
| 鳥啼流水落花外 人在春山暮雨中 |
|
| 【読み】 |
| 漫(まん)に道(い)う 桃源への路(みち)通ぜずと |
| 渓行(けいこう)十里 道心(どうしん)空し 鳥は |
| 啼く 流水 落花の外 人は在り 春山 暮雨の中(うち) |
|
| 【意味】 |
| とりとめもなく人は言う。桃源郷までの路は通じて |
| ないと。 渓に沿って十里余り入っても(桃源郷は |
| なく)禅師の心は虚しいばかり。 流れる水と散る花 |
| の向こうに鳥は鳴き、春山の日暮れのそぼ降る雨 |
| の中に人がいる。 |
| (この詩の訳の”禅師””人”は作者自身のことか?) |
|
| *漫道…とりとめもなく言う。これといった理由もなく、何となく言う。 |
| *渓行…陶淵明の桃花源記に「縁渓行 忘路之遠近」とある |
| *道心…仏教を信じ悟りを得ようとする心。転じて禅師のこと? |
|
| 【出典:山行(李柏・清)】 |
| ※起句・承句は資料がなく緑水のかってな解釈です。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
毎月の手本のページへ |
|
|